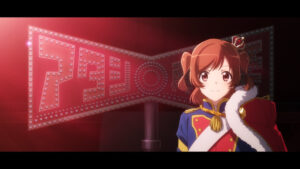まちは何かを生み出す原点のような場所だ。思えば、祭りや革命、テロリズムといった欲望の発露はすべてまちから始まる。しかし、テクノロジーの興隆によって欲望の発露の現場はインターネットに代替され、人口移動や高齢化などの目まぐるしい社会的変化のなかでまちは活力を失いつつある。そんないまを生きる僕らは、本当にまちに力や可能性があるのだと言い切れるのだろうか。
ラッパーのZeebraさんは、ヒップホップを通じて渋谷を夜の世界から改革しようと模索している。都心部の繁栄と地方部の衰退、全国各地のまちが激動の変化を迎える令和元年。主体性を保持しながら、常に社会規範に問いかけつづけるというヒップホップのマインドで現場からまちを変えていく彼に、カルチャーがまちを塗り替える想像力を伺う。
Zeebra:1971年生まれ。GRAND MASTER代表。1995年にキングギドラからデビューアルバム『空からの力』をリリース。1997年にはシングル『真っ昼間』をリリースしてソロ活動を始めるなど、黎明期から日本のヒップホップシーンを牽引している。またヒップホップ・アクティビストとして、2016年に「クラブとクラブカルチャーを守る会」会長として風営法の改正に導く。同年に「渋谷観光協会ナイトアンバサダー」に就任し、カルチャーからまちを変える活動にも取り組んでいる。

渋谷は変わる、ヒップホップは変わる。
—— Zeebraさんは日本のヒップホップシーンの黎明期から活動をされていますが、どのようにヒップホップと出会ったのでしょうか。
一番初めのきっかけは、ブレイクダンスを中学一年生ぐらいのときに知ったことですね。
1983年のアワードでハービー・ハンコックがライブパフォーマンスをしているのを見ていたときに、ロボットかと思った人が動き出して、「なんだこれ!」って。翌日から学校の廊下で真似してました。
アメリカでは同時期にブレイクダンスが取り上げられた映画「WILD STLE(83年)」や「Breakin'(84年)」なども公開されて、そういった映画のビデオが唯一のソースでした。
それと、DJも衝撃的でしたね。
みんなレコード盤というものは、端を丁寧に持って、慎重に置かないといけないものだと思っていたのに、その面を手でこすってスクラッチをするだなんて。
それをそれで形にしているところがすごかった。次第にDJにのめり込んでいきました。
それからビートも作るようになって。
ただ、ビートをつくっても誰かがラップをしないとラップの曲にならないじゃないですか。
それでDJをやる仲間同士でその問題を話しているうちに、俺がやる流れになって本格的にラップをやり始めたんですよ。
—— 1980年代中頃にはすでに日本にそういったカルチャーが入ってきていたのでしょうか。
いやいや、本当にそこからだったんです。
かろうじて、代々木公園の歩行者天国でブレイクダンスをやっていた人たちが一組いたくらいだったので、日本にはヒップホップの「ヒ」の字もなかった。
そんな状態が四、五年続いていくなかで、段々とDJカルチャーにハマりはじめた人も出てきて日本の状況が変わっていったという感じです。
—— どのように日本にヒップホップカルチャーは浸透していったのでしょうか。
ヒップホップだけではなく、クラブカルチャーっていうもの自体が日本に来たって感じですね。
それまで日本にあったのはディスコで、それはクラブとは大きな違いがあって。
ディスコはただ踊るための場所という感覚だから、言ってしまえば盛り上がることが一番正義。
毎日同じ音楽がかかるし、DJはディスコの店員さんがやる。それに対してクラブは文化みたいなものなんですよ。
月曜日は◯◯のパーティ、火曜日は◯◯のパーティ、みたいに毎回毎日違うジャンルのパーティをやっている。
だからDJを回すのは店員ではなくて、イベンターがブッキングしたDJなんですよ。
それまではクラブというもの自体が存在しなかったんだけれど、80年代中頃からでき始めていった。
そして世界的にもクラブミュージックブームが80年代中頃から後半にかけて盛り上がっていって、その流れと一緒にヒップホップが流行っていったんですよ。
—— それから90年代に入り、1993年にヒップホップグループ・キングギドラを結成し、1995年にはデビューアルバム『空からの力』をリリース。こうして渋谷から日本のヒップホップシーンを牽引されていきましたが、いつから渋谷が日本のヒップホップの中心となったのでしょうか。
実は、80年代後半の渋谷はチーマーだらけで物騒だったんだよね。
チーマー同士の喧嘩も多くて渋谷はだいぶ荒れていました。
一段落ついたのがちょうど90年代で、その頃から急速に渋谷にヒップホップカルチャーが根付いてきた印象があります。
—— なぜ、渋谷というまちにヒップホップカルチャーが急速に根付いていったのでしょうか。
とにかくレコード屋さんが渋谷に集中していたんですよ。
一時期、東急ハンズの一角にはマンハッタンレコード、シスコレコードのようなヒップホップの音源を取り扱うレコード屋さんがたくさんあったので、世界でも有数のレコード屋のタウン(通称・レコ村) (註1)と言われていたぐらい栄えていました。
海外から日本に来た人も、わざわざ渋谷のレコード屋さんに行って大量に買っていくぐらい特殊でしたね。
そういう意味では、渋谷はヒップホップが根付く土壌に恵まれていたのかなと思います。
夜に遊ぶ場所という点でも、クラブやディスコが特に多かったのは六本木と渋谷だったんですよ。
ただ六本木はどちらかというとディスコが中心だったし、バブルの名残があったので単価も高くて、お客さんも綺麗めな格好をしていましたね。
それに比べて渋谷は、よりカジュアルだったのでクラブが多くて。
だからヒップホップは渋谷というまちに馴染んでいったのだと思います。
—— 90年代から日本のヒップホップシーンは渋谷を中心に進んでいきますが、当時の渋谷はどのようなまちでしたか。
まず、いまと当時ではヒップホップの在りかたが違っていたので、まちの在りかたもいまの渋谷とは相当違っていましたね。
90年代の日本のヒップホップは、アメリカで始まったヒップホップをどれだけうまく日本にローカライズできるかを模索していた時期だったので、いまよりもっとコレクター気質があったんです。
つまり、ヒップホップが好きであるということは情報を収集することだったんですよ。
昔は、なにより情報量がかなり少なかったので、ヒップホップが好きなやつなら週に一回はレコード屋さんに行かないと話にならなかった。
特にレアものは三十枚しか入荷しないこともあるから、ゲトるには頻繁にレコード屋さんに通わないといけなかった。新譜が出たときも、その日に買わないと周りの話に乗り遅れてしまう。
俺はそんな訳にはいかなかったので、大体週三ぐらいは通っていましたね。
そういう事情だったので、俺のほかにもDJとかラッパーがよくレコード屋さんに買い物に来ていて、よくそいつらと会って情報交換をしていました。
渋谷はまち自体が媒体だったのかなと思うし、俺らの世代にとってはとにかくヒップホップとは追いかけるものでしたね。
—— 渋谷自体がヒップホップを知るための媒体となっていたのですね。まちとカルチャーが密接に繋がっていて活気を感じますね。
「渋谷ってすげえエキサイティングな感じがするぜ!」と思わせるような雰囲気を自分たちでつくっていくような感覚もありました。
レコ村には昼間でもヒップホップが好きなやつがいるから、用事がなくてもそいつらに会いに渋谷で集まるんですよ。
俺なんかは自分たちで折りたたみの椅子とかを持っていって道に座りだすし、他のやつらもラジカセを持ってきたり、路上でテープを売ったりしていて。
そうやってヒップホップが好きなやつらが渋谷に集まることで、自分たちで渋谷の空気をつくって目立とうとしていましたね。
—— ただ現在は音楽との関わりかたはまちに繰り出さなくてもスマートフォンだけで完結できるようになり、ヒップホップの在りかたも当時とは大きく変わっていますよね。
いまは当時のような情報量云々ではなくて、単純に音楽を楽しめるようになりましたよね。
追っかけるというよりは、SNSで簡単に情報を共有して自分の好きなジャンルの音楽を聴く時代。
ヒップホップという音楽ジャンルも、ビルボードのトップ10のほとんどを占めることはよくあるし、そういう意味ではヒップホップは世界のポップスじゃないですか。
つまり、もうどこにでもある音楽になったので、俺たちが路上でやっていた情報交換は、SNS上でやるようになっていった感覚があります。
ヒップホップをさらに日本に浸透させるには、音楽業界を牛耳るような明らかなヒットチューンを個々のアーティストが出す必要があると言われてるけど、それぞれが自分の好きなジャンルだけを追うようになった現状だと、そもそもそういうヒットチューンを生み出すのは難しい時代になっているのかなと思いますね。
ただ、当たり前のようにMステにラッパーが毎週一、二組出てくるような状況にはしたいし、個々がいろいろなことを試してみる時期なのかなと思います。
まちとカルチャーはつながっている。
—— Zeebraさんは自身の音楽活動と並行して、テレビ番組『BAZOOKA!!! (高校生ラップ選手権)』『フリースタイルダンジョン』の企画、日本初のヒップホップ専門ラジオ局WREPの開局など、さらにヒップホップカルチャーがはやるような環境づくりに力を入れていらっしゃいます。2016年には、まちとカルチャーをつなげるリーダーとして「渋谷区観光大使ナイトアンバサダー」に就任されましたが、どのような活動をされているのでしょうか。
よく芸能人のかたがたがやっている観光大使の夜版というスタンスで、渋谷の夜の楽しさをプロモーションする仕事をしています。
ただ、俺はその仕事だけではなくて、より行政に近いことをしてまちとカルチャーを両方盛り上げようと思っていて、それを実現しうる、「ナイトメイヤー」という新しい制度を整備しようとしています。
—— ナイトメイヤーとはどのような制度なのでしょうか。
読んで字のごとく夜の市長という意味で、行政における市長に対して、行政と夜のまちの仲介をする役割の担い手、いわば夜のまちのリーダーを擁立する制度です。
まちのなかでお店を営む上で生じた問題を、夜のまちを代表してナイトメイヤーがまちのかたと相談したり、行政に報告して新しいルールを整備したりして夜のまちをよりよくしようとする仕事なんです。
もともとナイトメイヤーの制度は、オランダのアムステルダムから始まりました。
制度が整備されてから深夜の犯罪率が三十パーセント減少したそうで、この制度には、まちと人々が同じ方向を向いていける力を感じています。
ちょうどいま、今年の十一月に渋谷でナイトメイヤーを決める選挙をやろうと動いていて、渋谷の商店街のかたがたにアンケートや直接でのお話を伺っているところで。
この前も道玄坂の商店街のかたにお話を伺いにいったら、「実際夜のことは、行政はなかなか注目してくれないよ」「そういうのができるのであれば、本当に頑張ってもらわないと」というお話をいただき、渋谷の商店街のかたがたの声は悲痛だなと感じました。
当たり前だけれど、昼間に働く人が夜中三時半に何が起こっているのかまで全部把握することは難しいことですよね。
だから夜に活動する人たちで夜のまちをコントロールして自浄作用を持たせる。
そしてときには行政と一緒になって何かを進めていけるとまち自体がもっともっと面白くなってきますよね。
—— ここまで先進的な取り組みを行うのは国内でも珍しいのではないのでしょうか。
実は渋谷区の行政にも実験的な取り組みに挑戦するスタンスがあって、結構協力的なんですよ。
以前、長谷部健渋谷区長と対談をさせていただく機会があったときに、彼から「渋谷から始まったカルチャーはすべてストリートから始まっています」というパンチラインが出たんですよ。
彼自身、進歩的な方針を持っているのだけれど、渋谷区としてもまちからカルチャーが生まれる意識が強いんです。
それだけ渋谷のカルチャーに誇りを感じてもらえている。
だから渋谷区は、なかなか試せないことにどんどん取り組んで先進的なモデルタウンになるといいなと思いますね。
そしてそこでうまくいったシステムがスタンダードになって、他のまちにも導入できるといいですね。
—— Zeebraさんにとって、渋谷というまちはどのようなまちですか。そして将来の渋谷はどのように変化していくのか、あるいは自分がどのように変えていきたいとお考えですか。
もちろん渋谷は長い歴史を持つ大きなまちであるけれど、俺も渋谷というまちと一緒に生きてきた感覚があります。
自分が学校の帰りにたむろしていた当時から現在に至るまで、俺はいろいろな形でその歴史に関わってきたと思っているから、いままでの渋谷の歴史と一緒に成長してきた感じがすごくある。
だからこれからも一緒に成長していきたいですね。
おかげさまで、日本で一番有名な観光スポットがスクランブル交差点になったそうで、そういう意味でもたくさんの外国のかたがたにも注目していただけるようになっている。
だからまずは、当たり前のようにアジアで一番渋谷がやばいと言われるような、アジアをリードしていけるようなまちにしたいですね。

カルチャーはまちを変革する。
—— 渋谷区は大きな将来性を持っていますが、全国のすべてのまちが渋谷区のように活性化しているとは言えない、という現状があります。過疎化や少子高齢化などのさまざまな問題が山積するなかで、これらのまちに再び活力を取り戻すためには何が必要だとお考えですか。
活力がないということは、そのまちには、大雑把にいうと「刺激」がないのだと考えていて。
ここで言う「刺激」というのは、ここにいたら何かが起きるかもしれないという可能性のことであったり、ライフスタイルで素敵だなと思わせるもののことを指しています。
つまり地元を出た若い人が自分の地元に戻りたくなる、あるいはそこが地元ではない人が遊びに行きたくなるようなものがないと、まちに活力は取り戻せないと思うんですよ。
過疎化や少子高齢化が進んだまちをいきなり渋谷みたいにするのはできないわけだからアプローチの方法は全然違うけれど、必ずどんなまちにも活力を取り戻すきっかけはある。
たとえば、年に一、二回大きなフェスがあるだけで、そのまちは有名になりますよね。
そういう風に外からの働きかけとそのまちの歴史やライフスタイルとをうまく結びつけながら、その地域ならではのものが生まれたら面白いのかなと思います。
—— 日本全国のまちを「刺激」あるまちに変えていく上での着眼点はありますか。
俺は、特に夜の使いかたをもう少し考えたほうがいいと思っています。
最近は、神社とかお寺でも、深夜までパーティをやったらいいじゃんとよく言っているんですよ。
ただ、日本ではまだ深夜は寝るものだと思う人や、歴史的、文化的な空間をそういう使いかたで、しかも深夜に使うというのはありえないと思う人が出てくるかもしれませんね。
—— 確かにいままでにないアイデアですが、なかなかの反発も想定できます。
でも、よくよく考えたら、神社ってみんなにとって一日中安心できる場所なんですよね。
この前、子どもたちだけで元日の深夜に初詣に行くって言い出したとき、そんな夜の時間帯に外に出ても補導されないかと思ってググったことがあったんです。
そうしたら、正月の深夜の神社はどうやら補導されないらしくて。
つまりそれぐらい神社はみんなが安心できる場所として認めてられているということなんですよね。
せっかくそういう場所があるのであれば、もっと若い人たちと年配の人たちの世代がそこで一つになっていければ本当にいいのになあと思います。
あとは、世界的にみてもある意味では欧米化がガンガン進んでしまっていることを考慮する必要があると思います。
大部分の建物は日本家屋というよりかはビルだし、俺らはいま当たり前のように洋服を着ているわけだし。
歴史的な空間であることを理由にしてそういうことをするのはけしからん、と頭ごなしに否定するのは違うんじゃないかと思います。
とにかく日本は無駄に遵法意識が高すぎるので、そこの枠から外れることを考えることすら「反社会」になってしまう。
でもその「反社会」のラインの引きかたは間違っていると俺は思うんですよ。
—— 何が正しいかを考えること自体はむしろ社会にとっても有益なことですよね。
そうですね。だから昔からある祭りをいまの祭りにアップデートさせるつもりで、もっとDJが出て、みんなでガンガン盛り上がって、みたいなものをやれればいいなと思っています。
そういうなかから、伝統的な日本らしさといまの時代背景とが一緒になった、新しい日本らしさが生まれてくるのだと考えています。
—— まちを変えていくために必要なマインドとして、古来の文化へのリスペクトと新たなカルチャーを受け入れる寛容さが希求されるのですね。
あと、もちろん必要なのは、自分たちがまちを変えていくという感覚だと思います。
たとえば、ヒップホップの四大要素の一つであるグラフィティーカルチャーには、そのメンタルとしてヴァンダリズム(註2)が持つ権力や社会へのメッセージという観点に加えて、実はアートによるまちの美化という観点もあるんですよ。
そもそもまちをアートで埋め尽くそう、という考えからグラフィティが始まっているところがあります。
だから、シャッター街にあるシャッター全部を超かっこいいグラフィティーで埋められたら、新たな観光スポットとして多くの人に注目してもらえるかもしれない。
一時期、横浜の桜木町もグラフィティーアートが広がっている高架下のエリアが観光名所になったことがあるくらいだし。
そういう、みんなでペンキを買ってきて塗ったりする感覚が大切だと思っています。
どこどこの業者にタイルを頼んで、施工業者にタイルをつけてもらうのではなくて、ときには自分たちでいまあるタイルの上から塗ってしまえ、という感覚が過疎化したまちに求められているマインドだと思います。
自分たちの周りにある味気ないものを自分たちで楽しいものに変えていけばいいという感覚は、ストリートゲットーの知恵として昔からある考えかたなんですよ。
—— 変革は自分自身が主体となることで実現する、このヒップホップのマインドがまちに「刺激」をもたらすと。
そうですね。ときには誰かが変えてくれることもあるけど、誰かが変えてくれると思っているだけではなかなかうまくいかないよね。
一人ひとりが変えるんだという自覚は、何かを変えようとする上では当たり前のことだと思います。
選挙だって「俺一人が行っても国は変わらない」と思っていたら当然変わらないわけで、それとまちを変えることは同じことですよね。
まちと関わることをめんどくさがったり、ただ現状を否定したりするだけではなくて、常に何が正しいかを考え続けながら地道に実を取ることが一番大事なことなんじゃないのかな。
突然に状況がひっくり返ることなんてそうそうない。
それでも世の中は自分たちの手で変えられるものだと確信しています。
本気で大切なものを語れば、そして動いていけば、ルールを変え、世の中をも変えられる。
だから自分がこれはこうあるべきだと思うのならば、どんどん動いていくべきだと強く思います。

(註1)渋谷区宇田川町にあった、90年代におけるレコード屋が集中していた地域の愛称。
(註2)文化財や公共物を破壊する行為のこと。一般に忌避される行為であるが、権力や社会に対するメッセージが内包されており、ストリートアーティストのバンクシーのように評価される場合もある。