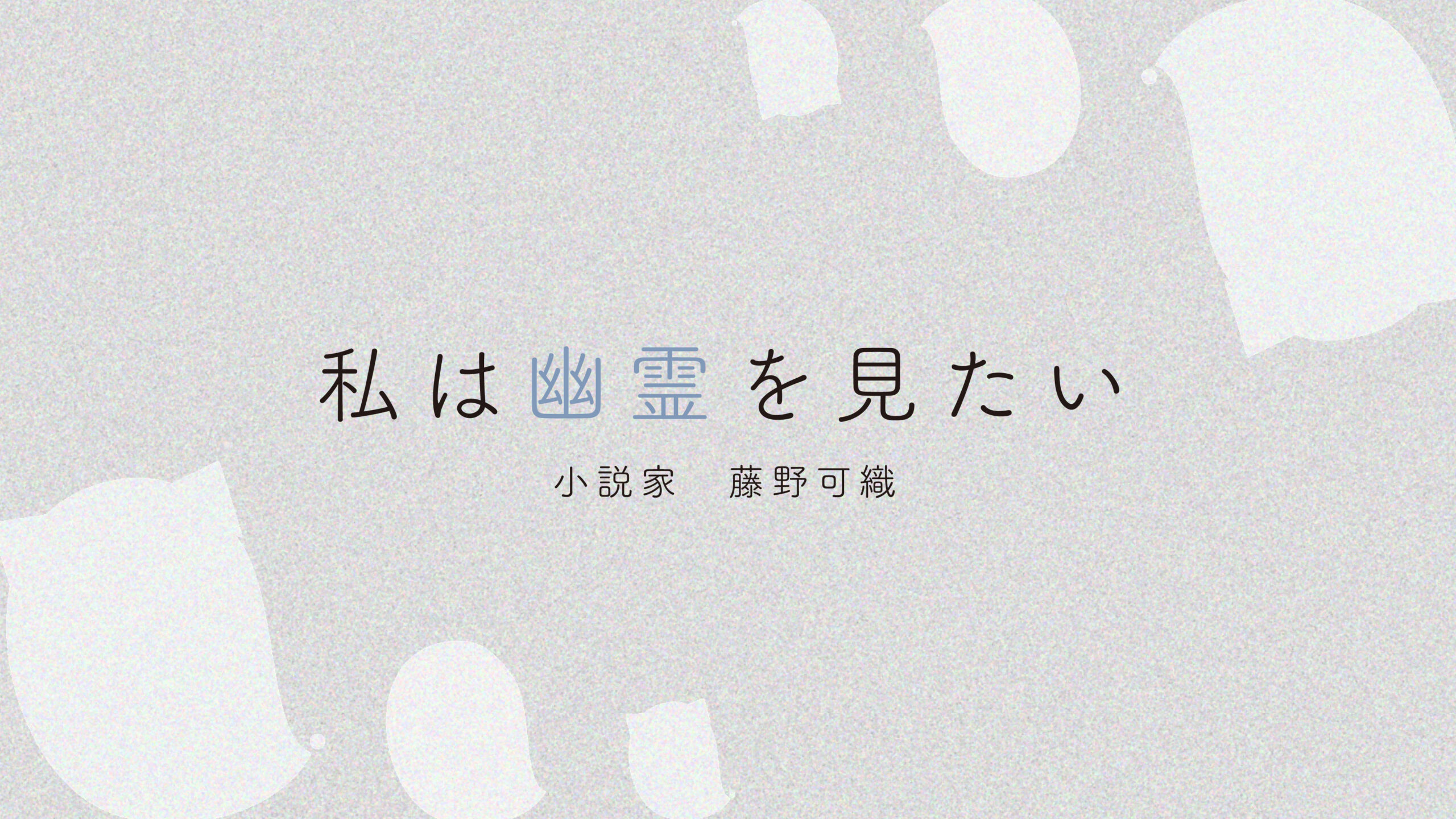幽霊を信じていなくても、見たことがなくても、怖がりでも、幽霊について考えてみる。そのうち、何かが見えてくるかもしれない。それはぞくぞくするような恐ろしい幽霊の姿か。それとも、火の玉の形をした物言わぬ隣人か。私たちが最期を迎えた後のその先にあるステージそのものかもしれない。正解は未だ誰にもわからない。凝り固まった幽霊観を捨て、幽霊をさまざまな角度から考えることができれば、あなただけの幽霊の形が浮かび上がってくるだろう。
藤野可織さんは、幽霊を追い求めた小説家である。生粋の怖いもの好きである藤野さんは、霊感が全くないと自称しながらも怪談雑誌にエッセイを連載した経験を持つ。本記事では、『私は幽霊を見ない』としてまとめられた一冊の中で「幽霊を多様な視点から考えること」を実践した藤野さんにインタビューを行った。
藤野可織
2013年に『爪と目』(新潮社)で芥川賞を受賞。不穏な空気が漂う作品や不思議な世界観を持つポップな作品に定評がある。近年は女性の活躍にスポットライトを当てた作品でも注目を集めている。著書には『来世の記憶』『私は幽霊を見ない』(共にKADOKAWA)『おはなしして子ちゃん』『ピエタとトランジ』『青木きららのちょっとした冒険』(共に講談社)などがある。
エッセイ『私は幽霊を見ない』
―藤野さんが幽霊に興味を持ったきっかけはありますか。
なんといってもまず、周りに怪談話がすごく溢れていたんですよね。時代なのかもしれないんですけど。小学校に入るやいなや、いわゆる学校の七不思議みたいなものが身近になって。最初はすごく怖かったんですけど、段々と幽霊に興味を持つようになりました。
―やはり土地柄もあって、お住まいの京都の方では幽霊が身近に存在するのでしょうか。
土地柄かどうかはわからないですけど、そういえば京都の親鸞にゆかりがある学校に、親鸞の幽霊が出るという話を聞いたことがあります。どうしてそれが親鸞と特定できるのかはわかりませんが、歴史上の人物の幽霊が出るっていうのは面白いなと思いますね。
―怪談を集めて気づいたことはありますか。
「幽霊を見たことがありますか?」と聞くよりも、「あれはなんだったんだろうっていうことってあります?」と聞いたほうが、「そういえば」と話をしてくれることが多いと気づきました。恒常的に見えている人や、普段から自分はばっちり怪異が見えているということを自覚している人というのはなかなかいないという印象があります。
―怪談雑誌の連載を受けたときから、エッセイの方向性は定まっていたのでしょうか。
そうです。東雅夫さんが編集された『私は幽霊を見た』という実話怪談集があったんです。それがすごくいいタイトルだなと思って。タイトルはそれをもじってつけました。私は幽霊を見たことはないから、そのまま正直に。
幽霊と物語
―エッセイのテーマは幽霊でしたが、藤野さんご自身の創作スタンスについても述べられていましたよね。
そうですね。小説を書くときの私は、特に関係のないどこかから派遣されてきた記録係で、単に目の前で起こっていることを見て記録しているというふうに自分で思うようにしているんです。だからこの小説の世界の中から見ると、小説を書いている自分は幽霊に近いなということをすごくよく感じます。
あと、普段本を読んだり映画を見たりしていても、物語の世界には私たちは介入できないじゃないですか。だから、そういうときも、読者とか観客というのは幽霊に近い存在なんじゃないかなと思うことがあります。
―藤野さんの作品には幽霊に関する話や不思議な話が多いですよね。
そうですね。幽霊が直接的に出てくるものはそんなにはないんじゃないかなと思うんですけど、確かにおかしなものが出てくるものは多いと思います。それはもちろん怪談が好きということもあります。あとは、美術が好きなので、むしろそういうものが物語に出てくる方が私にとっては自然なんです。美術館などで絵を色々見ていると、実際のこの世の物理的な法則とは別の法則で書かれていたり、妙な怪物とか悪魔とか、そういうモンスター的なものが描かれていたりすることがとても多いので。
―私たち人間はどうして幽霊に惹きつけられるのでしょうか。
それはやはり、幽霊が人間の鏡像だからだと思うんです。私は自分自身幽霊が見えないし、見たことがないこともあって、現実に幽霊はいないと思っています。それでも、色々な物語に幽霊が出てくるのは、幽霊としてしか語れないものがあるからだと思っています。
―鏡像というと、生きている私たちが、ある種都合の良いように幽霊に語らせているという見方もできる気がします。
私たちが生きているときにできないこと、過去に生きてきた人が生きているときにできなかったことが、幽霊というものに託されているというのは、もちろんそうだと思います。でも物語では、幽霊が生きている私たちに都合がいいばかりではないと思うんですよ。
幽霊が私たち人間にとって都合がいいものとして楽しく描かれてるものもあると思うけれども、幽霊によって最悪な状況になるという話もたくさんありますし。
―藤野さんの小説は純文学ホラーと呼ばれることもあり、怖いという評価も多いと思うのですが、怖いという感情についてはいかがでしょうか。
単純に好きだからというのもあるんですけども、私は、物語は怖い方がいいと思っているところがあるんです。でも実際に怖い思いをするのは嫌なんですよ。幽霊とは関係なくても、色々怖い思いをしたことを思い出すと、もう二度とああいう体験はしたくないなと思います。でもだからこそ、その分物語は怖くあるべきだと思っています。
本当は楽しめないものを、物語では楽しむことができるというのが物語のいいところで存在意義の一つだなと。怖いというのは実際には楽しめないけれども、物語の中では楽しめるものにもなるなというのは、いつも思っていることです。
もしも幽霊になれたら
―幽霊のアイデンティティについてはいかがでしょうか。
そうですね。幽霊になったときにどういう状態になるのかということを想像するのは楽しいですね。自分のこの体のまま幽霊になるのか。もう体の記憶のことなんかどうでもいいなと思った瞬間から完全に違う姿になれるのか。服はどうするのかとか。着替えたりできるんですかね?あるいは、そもそも人じゃない、人魂みたいな形かもしれない。私たちは、実際に在る物理的な肉体に縛られている場面ってものすごく多いですよね。逆にそれがあるからこそ、とりあえず自分のアイデンティティの方向性が決まってくるっていうところもあると思うんですけど。だから幽霊になったら自由かもしれないけどもしかしたらその自由のせいですごく困っちゃうかもしれないし、そうじゃなくてはじめて自分はこうだったんだっていう姿を獲得できるのかもしれないし、その辺はどうなんだろうなって。こうやって考え始めると、色々小説が書けそうな気がします。
―もし幽霊になるとしたらどんな幽霊になりたいですか。
私がもしも幽霊になったら、一日中映画館にいて、無料でいろんな映画を見てみたいと昔からずっと思っていました。美術館とか博物館にも行きたいなって。生きている今でも行けるんですけどね。
―ふわふわ飛んで、無料で見れたりとか。
そう。はしごできたりとか、夜間も見れたりするのがいいな。美術館だと閉館しても入れるだろうし。幽霊がみんなで作品を鑑賞してたらいいですね。
エア猫と子どもと幽霊と
―エッセイの中に、幽霊が無意識のうちに見えてくるものであるとありましたね。その中で、意識しないと見られない幽霊未満のものとして、想像上の”エア猫”を挙げていましたが、現在はいかがですか。
エア猫は、私が子どもを産んでから子どもを怖がって隠れるようになりました。というよりは、もう私がエア猫に構っていられなくなってしまったんです。でも不思議なことに、今は子どもが自分の頭の中で猫を飼ってるんですよ。
―それはもちろん”エア” なのですか。
はい、エアです。この話を子どもにしたことはなかったのに、子どもはエア犬も飼っています。いつも自分の架空の猫と犬の話を私にしてくれるんです。
―子育てをされる中で幽霊に対する考えに変化はありましたか。
子育てをしていると、本当に子どもはお化けとか妖怪とかが好きだなと感じることが多いです。そして、日本の社会では、子どものためにお化けとか妖怪がたくさん用意されているなということにも改めて気がつきました。今は子どもと一緒に私も楽しんでいるところです。
―文庫本の書き下ろしの方では、幽霊と子どもが似ているという話もありましたね。
一つは、幽霊も子どもも、コミュニケーション手段が大人同士とは違うという意味で書きました。もし幽霊が本当にいたとしても、なかなか私のような鈍い人間にわかってもらうのは大変そうだと思って。私は幽霊のやり方を習得できないししようともしないし、幽霊のほうが習得してくれないとどうしようもない。子どももすごく幼いときは、まだ私と共通のコミュニケーション手段を習得していなくて、もちろんこちらも相手を理解しようとしているんですけど、相手のやり方を私が習得するんじゃなくて、相手に私のやり方を習得させようとします。こちらが当然だと思っているコミュニケーション手段、通信手段のようなものから疎外されているという意味で、幽霊と子どもには共通しているところがあるなと。物語の中でも子どもと幽霊が近づけて描かれたり、両者が友達になったりするということがよくありますし。最初に子どもからおかしくなっていくという展開も多くありますよね。
もう一つは、大人にとっての子どもと幽霊が似ているのではないかという意味で書きました。先ほどお話したように、物語上では子どもと幽霊というのは近しいものとして描かれることが多いんです。小説を書いている人や映画を作っている人たちは、みんなある程度大人じゃないですか。私たち大人にとって子どもというのはずっと残響というか、自分の中で反響しているものだと思うんです。そして幽霊というものも、やはり人間にとっての残響のようなものなんじゃないかと思うんです。それで、大人にとって子どもと幽霊は似てるのではないかと。この場合の子どもは、実際の子どもじゃなくて自分の中の子どもという意味です。
実話怪談と幽霊の役割
―エッセイの中では、心霊写真についてのお話もありましたね。
私は大学院で写真研究をやっていたんです。それもあって心霊写真には興味があります。心霊写真は写真の黎明期からトリックでつくられてきました。写真と心霊というのはすごく関わりが深いなと思っています。
今はデジタルの時代ですから、心霊写真が撮れたとかあんまり言わなくなってしまったんじゃないでしょうか。全盛期は過ぎてしまったのかなとちょっと寂しく思っています。スマホで簡単に加工できちゃいますし、もうそんなにありがたくもないですよね。
―幽霊について、日頃から考えることは多いのでしょうか。
そうですね。幽霊については、実在するかどうかではなくて、物語の中でどのように必要とされているかということが一番の関心事です。どのように私たちは幽霊が必要なのか、幽霊にどういう役割を負わせようとしているのか。
幽霊という装置を通すことによって、なにをどのように語ることが可能になるのかということをよく考えています。
―幽霊の役割といえば、危ないところに近づかせないために「あそこにはおばけが出るよ」と言うこともありますよね。
幽霊が出るからという言葉を聞いただけで、暗かったりジメジメしてたりするんだろうなというイメージも一緒に喚起されるということはありますね。幽霊という言葉ひとつで、読み手側が受け取るメッセージや印象の方向性が決まってくるところがある。それもやっぱり、幽霊というものに託された役割の一つだと思います。
私も、早く寝ないとおばけが来るよって子どもに毎晩言ってしまってますね。子どもの健康のためでもあるし、子どもに早く寝ついて欲しいという大人の都合もあって。子どもに言うことを聞かせるために、おばけや幽霊を引き合いに出すのはすごく有効だなと思います。幽霊を便利に使わせていただいていますね。
―実話怪談がお好きだそうですね。
そうですね。実話怪談は毎月ものすごくたくさん出ていて、全部読み切るのは難しいのですが、熱心に読んでいます。実話怪談は全部が本当にあった話であることが前提なんですけれども、私はその辺をめちゃくちゃ大切にしてるわけでもないんです。それよりも先ほど言った通り、幽霊というものがどのように語られているのか、どういう扱いを受けているのかということにすごく興味があるので、それについて頭の中で統計を取るように読んでいます。最近はこういう感じで描かれる傾向があるなとか。
―ちなみに、最近はどんな怪談が流行しているんですか。
ワンパターンから脱しようという気合を感じますね。よくある話は不採用になってるんでしょうね。
ホラー映画でよく出てくるステレオタイプの女性の幽霊は、意外と書かれなくなってるなあとなんとなく思っています。実際に数をちゃんと数えたわけではないのですが、私の読んでいる体感として。
あとは、過去の因縁がなんとなくわかるタイプと、もう全然因果関係がわからないタイプのものがありますね。他には、なんとなくぼんやり怖いけど、これは幽霊なのかどうなのかもわからないというものも結構多いですね。
―藤野さんはそういった因果のわかるタイプとわからないタイプ、どちらがお好きですか。
私はどっちも好きです。でも私は自分が思いつかないような不思議な話を読むとすごく嬉しくなるので、どちらかというとわけがわからないタイプが好きですね。
例えば、これももうパターン化してきている気はするのですが、最近、足元に何かがまとわりつく感じがする。もしかしたら、死んだペットが帰ってきてくれたのかもしれない。そう思って足元を見たら、まさかの人型の幽霊で、それも全然知らない人だったとか。わけがわからなくて不気味ですよね。親しい存在の霊だと思ってたらちがった、みたいなタイプはいくつか読んだおぼえがあります。自分の人生を物語として理解したいという幻想を打ち砕く、という物語のパターンとでもいうのでしょうか。
あとそれから、未だに狸と狐が化かした系もあるんですよ。これも本当にすごく好きです。
不思議なことが起きて、あ、それは狐の仕業だよって年長の人に言われて終わる話とかちょこちょこあります。とっくに捨ててしまった物語が追いかけてきてくれたみたいな気持ちになりますね。
―私たちは人間の先にあるものとしての幽霊に面白さがあると考えています。 人間と幽霊という二項対立についてはどうお考えですか。
私は幽霊という状態はないと思っています。つまり、人間の先にはなにもないと思っているんです。ただ、人間は、人間という存在だけで生きていくのが難しいんだろうなと思うんですよ。その続きとか、それ以前の何かがきっと必要なんです。それで幽霊というものが発明されたんではないでしょうか。それから先程の、物語の作者や読者は物語にとって幽霊に近い存在なのではないかという話ですが、幽霊の性質と物語の性質は似通っていると言い換えることもできると思います。
だから幽霊というのは私にとって物語なんですよね。物理的な存在というより。私たちに物語が必要であるということと、幽霊が必要であるということは多分ほとんど同じ種類のことだなと思っています。
―植物の幽霊のお話もされていましたね。
そうですね。植物の幽霊を見てみたいって書きましたね。うちにあった観葉植物は全滅したといっても過言ではないのですが、私はまだ植物の幽霊にも会えていませんね。
そういえば、実話怪談で植物の幽霊というか、精霊の話を読んだことがあります。おばあちゃんが椿の木の手作りのおはぎをお供えしたら、夢の中にその椿が出てきてずるずる歩いて近づいてきて、「こしあんがいい」ってお願いしてきたっていう。このお話はすごくすごく可愛らしくて大好きです。
怪談を話す
―大学やイベントなどでお話をされる機会も多いと思うのですが、そういった場で怪談を聞いたりしますか。
そうですね。『私は幽霊を見ない』の中でも、私が京都精華大学で非常勤講師をしていたときに学生さんたちから聞いたお話を書きました。とはいえ、聞いたら出てくるけど、学生さんたち同士で普段から積極的に怖い話をし合っている様子ではなさそうだなとは思いました。皆さんはいかがですか。
―私たちもあまり怪談を話す機会はないですね。私自身も今回の企画をきっかけにして同級生に怪談話を聞いて回ってみたのですがなかなか出てこなくて。
でもこの前に私自身が怖いと思った話なら、一つあります。私がラーメン屋でアルバイトをしていたときのことです。私のアルバイト先のラーメン屋は、閉店後も注文のシステムだけは電源をつけたままにしているんです。だから、店の電気が消えたあとも厨房の注文パネルだけは光っている。そして、その日もお店の締め作業を終えて店内の灯りを消していました。それなのに、最後に店長と一緒に帰ろうというときに、ピロンって音が鳴って。厨房の注文パネルが光ったんです。誰もいないはずのカウンターで塩ラーメンが注文されていました。
幽霊が塩ラーメンを注文したのでしょうか。めちゃくちゃいいお話ですね。
―そうですよね。それに盛り塩みたいに幽霊は塩ラーメン食べるとそのまま成仏してしまわないのかなというところもすごく気になります。
なるほど。それも面白い発想ですね。1Kさんはどうでしょうか。怪談話とか。
(担当編集Kさん)
私は仕事柄、色々な人にお会いするので不思議なお話を聞くこともありますね。例えば、私が担当している、お医者様で小説をお書きになってる先生から伺ったことがあるんですけど、人は亡くなる二週間前に、ほとんどの人が幽霊を見るんですって。そういう発言をし始めると、もうお迎えが来たって看護師さんは先生に伝えに行くらしいんです。すごく小さい人だったりとか戦死した父親だったりとか、あるいは大名行列みたいなものだったりとか、人によって見るものは違うらしいんです。それでも、それらを見た人は確実に二週間後にぴっかり亡くなるというのは共通しているそうです。脳の一部が死の準備をするときに、そういう映像を見せるんだと聞きました。
―これまでとは違った幽霊のお話ですね。
幽霊がいるのかいないのかはわからないけれども、脳が見せる一種のバグのような現象として幽霊を見るということがあるのかもしれない。それを私たちは物語の中に置き換えて考えているのかなとか、だから本当は幽霊を見るという能力は人間本来が持っているちょっと不思議な力なのかなとか、思ったりもします。
(藤野さん)
自分は最期にどんなものを見るんだろうと考えると面白いですね。私は怖くないものが見たいなと思っちゃいます。
―みなさん、素敵なお話ありがとうございました。エッセイの続きがあったらぜひ読みたいです。
ありがとうございます。まだ書いていない話もあるので、いつかどこかで書くことができたらいいなと思っています。
- 今回の取材では藤野さんの担当編集であるKさんにもご協力いただいた。 ↩︎