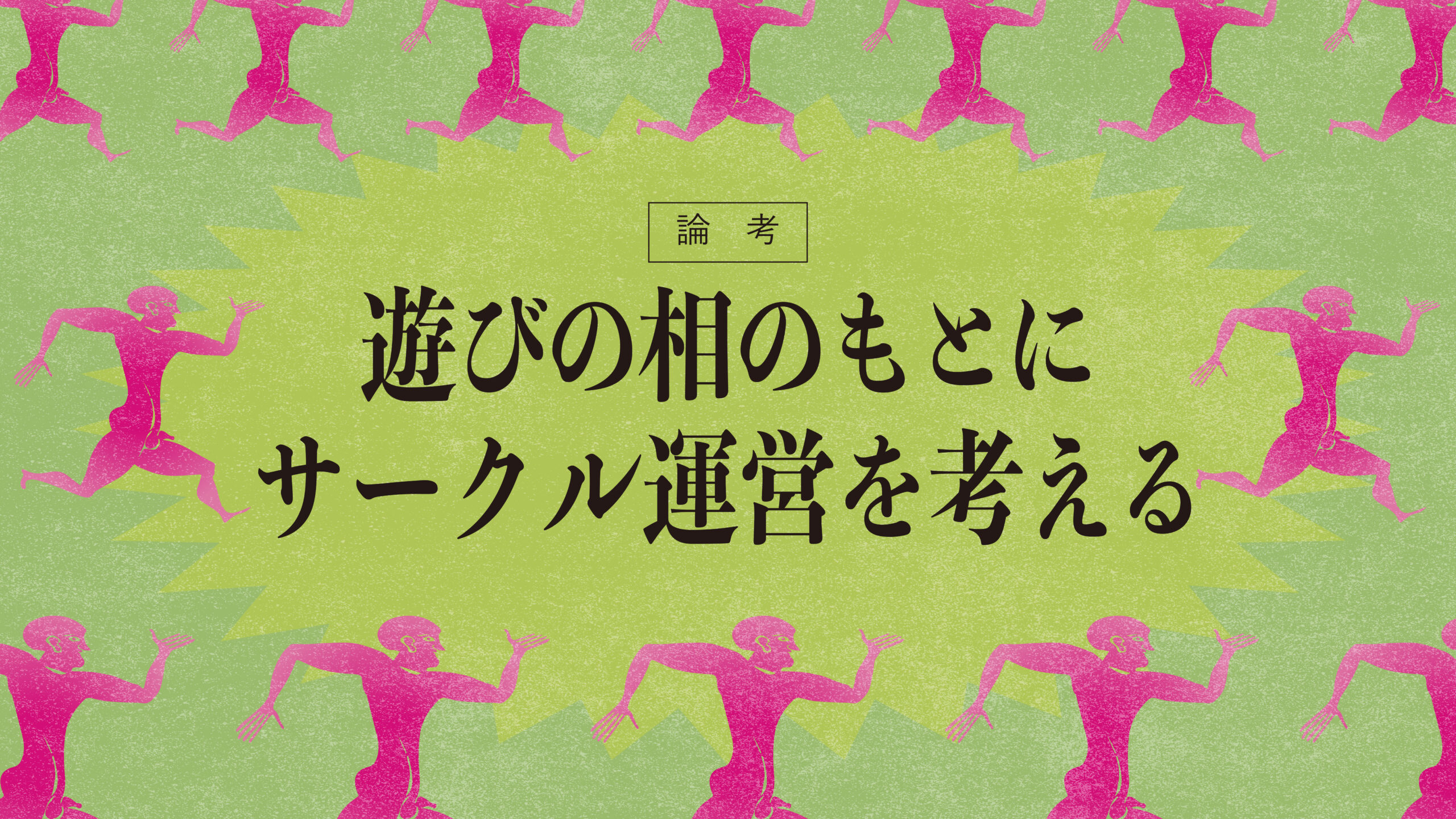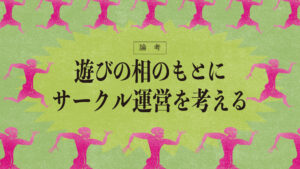サークルはそもそも「組織」なのか
サークルという「組織」を上手にマネジメントしていくことは、あまりにも難しい。
多くのサークルに当てはまると想像するが、活動を続けていくうちにモチベーションに差が出てきて次第に中心と周縁が生まれ、一人、また一人とサークルから姿を消していってしまう。この「組織」の問題をどう考えたらよいのだろうか。
アメリカの経営学者バーナードは、組織の三要素として「コミュニケーション」「貢献意欲」「共通目的」を挙げ、どれか一つが欠けると組織として成り立たないと説いている。
「コミュニケーション」の保持に関してはサークルでも工夫のしがいがあろう。実際にこの雑誌を制作している早稲田リンクスでは今年から連絡手段を見直し、オープンなコミュニケーションを心がけた結果、意見交換が活発になり活動そのものが盛り上がってきている実感がある。
しかし「貢献意欲」「共通目的」を保つには不利な点がある。
まず、企業とは異なり、サークルでは対価・報酬をメンバーに支払うことはない。そのため、サークル運営において「貢献意欲」を報酬によって引き出すことはできない。また、企業では勤務時間が設定されているのに対し、サークルでは活動への参加は原則自由である。そのため、メンバーのコミットメントを強制的に上げて「共通目的」を浸透させることもできない。特に早稲田リンクスはそもそも活動内容が多岐に渡っており、各人がやりたいことをできる環境を魅力として考えているため、「共通目的」を共有することのハードルはさらに高い。
バーナードによれば「共通目的」を共有していない場合は「組織」ではなくただの「集団」、つまり独立した個人の偶発的な集まりであるという。確かに、同じサークルに所属している人でも、純粋にその活動を楽しみたい人、友達を作ることを目的としている人、ガクチカのために活動している人など、それぞれ別の目的を持って参加しているように思う。そう考えるとサークルとは「組織」という大層なものではなく、ただの偶発的な個人の「集団」と言った方が適切であるかもしれない。
しかしどの経営理論も、マネジメントする対象が「組織」であることを前提に論じていて、サークルのようなふわっとした集まりに関する理論などあまり見聞きしたことがない。
サークルを上手にマネジメントしていくためには、やはりメンバーを選抜するなどして、サークルをもっと「組織」らしくしていくしかないのだろうか。ふわっとした集まりを、ふわっとしたまま維持するなんて方法は、考えられないだろうか。
ホイジンガの議論を参考に、サークルが「遊び」である可能性を考える
そもそもサークルには共通の目的がないにも関わらず、一体なぜ人が集まって活動できているのだろうか。これを考えるために、人間や動物が目的もなくする行動であると主張される、「遊び」に注目したい。
「遊び」についてそう主張するのは、オランダの文化史家ヨハン・ホイジンガである(註1)。彼は「ホモ・サピエンス(知恵のある人)」を「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」と再解釈し、古今東西のあらゆる人間文化の中に「遊び」の要素を見出した。
ホイジンガによると、従来の「遊び」に関する分析は全て、「遊び」には遊ぶこと以外の目的があるという前提から話を進めているが、そういった類の説明はどれも「遊び」の部分的な解釈でしかないという。
私たちが遊ぶとき、「有り余る生命力の過剰を放出するため」とか、「緊張から解きほぐされるため」といった目的は一切意識しておらず、「子犬が戯れる」のと同じように、遊んでいるその一瞬一瞬が本能的に楽しく、ただ単に面白いと感じてやっている。
「遊び」の本質とは「面白さ」であり、「面白さ」は「それ以上に根源的な観念に還元できない本質的なもの」であるという。つまりホイジンガは、人や動物が遊ぶのは何か他の目的のためではなく、ただ純粋に面白いからであり、遊ぶことそれ自体を目的として遊んでいると主張する。
これと同じようにサークル活動も捉えられないだろうか。すなわちサークルには活動を通して達成したい目的は特になく、サークル活動がただ純粋に面白く、活動することそれ自体を目的としている、ということである。
自己満足というと聞こえは悪いが、要するにそういうことであり、素晴らしいサービスや表現を生み出して世界を変えよう、社会に役立とうとするよりは(もちろんそういう意識の人もいるだろうが)、小学生の頃の休み時間に校庭で無邪気に鬼ごっこをしたり、教室で意味もなく絵を描いたりして「遊んでいた」あの感覚の延長でサークル活動を続けている人が多いのではないだろうか。
他にも、ホイジンガが考える「遊び」の形式的特徴と、サークル活動の性質に共通点がいくつか見られる。ここでは、「遊びへの参加が自由である」と「遊びには固有の秩序がある」の二点に絞って言及したい。
一点目の「遊びへの参加が自由である」とは、つまり「遊び」への参加を誰かに強制されることはなく、それぞれが参加するかどうかを自由に決められるということである。一般的な語の用法からしても、誰かに強制された瞬間、「遊び」の定義を逸脱し、普通「仕事」と呼ばれてしまうので、なんとなくその論理は直感できるだろう。
そして同様に、サークル活動をやるかやらないかも自由である。参加することも辞めることも本人の自由であり、部活動や企業に比べて圧倒的にメンバーが流動的であることがそれを証明している。個人の「やりたい」という意志が重視され、誰かにタスクを強制することが忌避される傾向にあるのも、サークル活動への参加が「自由」であることの裏付けだと言える。
二点目は、「遊び」には固有の秩序があり、それをもって「遊び」の世界の中と外が区別されているということである。
具体例としてトランプの大富豪を考えてみよう。当たり前だが、トランプのカードと人がそこに存在するだけでは大富豪は成立しない。「一人ずつ順番に場にカードを出す」や「2が一番強く3が一番弱い」といった約束事をみんなで共有し、そのルールに従い、そのルールの内側で真剣に駆け引きをすることで大富豪という「遊び」が成立するのである。ルールがあるからこそ「遊び」が成立し、「遊びの中」には必ずルールが働いているのである。
そして同時に、「遊びの中」のルールが「遊びの外」=日常世界に影響を及ぼすことはない。たとえ大富豪で負けて大貧民になってしまったとしても、それはあくまで大富豪という遊びの中での結果なのであって、現実にお金や名誉を失うことはない。このように「遊び」は固有の秩序をもって日常世界から切り離されているのである。
同様に、サークルについても固有の秩序があると考えることができないだろうか。例えば「毎年代替わりをする」「重要な手続きには全体の承認をとる」といった約束事があり、サークルの中にいる人がそれに従うことによってサークルが成立しており、ルールはサークルの中にだけ働いている。
特に早稲田リンクスでは、なんらかの企画の収支が赤字になったとしても、それをサークル員に肩代わりさせることは極力避けているのだが、その配慮は、サークルの中で起こったことがサークルの外(個人の日常世界)に影響を及ぼさないようにするための制度だと考えられる。そういった秩序が、サークルを日常世界から切り離し、「遊び」たらしめるための結界として機能していると言ってもよい。
ここまで見てきたようにサークルは、自己目的性、参加自由性、固有の秩序による日常世界との分離という特徴を持っている。これらの特徴はホイジンガの唱える「遊び」と共通しており、その意味でサークルは「遊び」的であると言えよう。
そのため、サークルになぜ人が集まって活動できているのだろうかという最初に立てた問いに対しては、「遊び」と同様、サークルで活動することがそもそも「面白く」それ自体を目的として活動しているからとここでは答えることができる。
シカールによるもっと柔軟な「遊び」の捉え方
ホイジンガの「遊び」の議論を参考に、サークルに人が集まってくる理由は「遊び」のそれと相似しているという認識に至った。
しかし依然として残る問題は、各人が「ただ純粋に面白いから遊んでいる」ことによって成り立っているのがサークルであるが故に、「面白くなくなったら遊ばなく」なり、サークルが次第に縮小していってしまうことである。
しりとりが長く続きすぎたり、誰かの番でずっと考え込まれたりすると自然とやめてしまうように、「遊び」がつまらなくなったりそれに飽きたりしてしまったら、それだけで「遊び」の世界は一瞬にして立ち消えてしまうのである。
では、メンバーにとってサークルを「面白い」ものにし続けるためにはどうすればよいのだろうか。
ここでもう一人、ホイジンガよりも「遊び」を広く柔軟に捉えたミゲル・シカールを紹介しよう(註2)。著書『プレイ・マターズ』において彼は、ホイジンガ以来の遊び観を大きく転換させている。
シカールによれば、ホイジンガが強調した「日常世界と切り離された別世界としての遊び」は「遊び」の一つの形態であるに過ぎず、「ゲーム」と言った方が適切だという(以下、ホイジンガが捉える遊びを「ゲーム」と呼ぶ)。
シカールはより人間中心的に「遊び」を捉えており、「人間がものや制度を使うそのあり方」までを含めて「遊び」だとしている。「ゲーム」だけに注目したホイジンガとは異なり、シカールはあらゆるものや制度を使って「遊び」を考え出す人間の「遊び心」や「いたずら心」に注目し、「遊び」の概念を拡張させた。詳しい議論が気になる方はぜひ彼の著書をあたってほしい。
ホイジンガとシカールの遊び観の違いは、スポイルスポート(ルール破り)に対する姿勢によく現れる(註3)。ホイジンガは、「ゲーム」はルールなしには成立しないと考えており、ルールが破られる=「ゲーム」の消滅であるとしているため、スポイルスポートは厳しく取り締まられなければならないと考える。
対してシカールは、ルールは「遊ぶという目的に対する手段」に過ぎないと考えており、ルールで遊ぶこと、すなわち「ルールを考え、操作し、変更し、適合させる」ことも「遊び」の構成要素になりうると主張する。
筆者なりにまとめるならば、既存の秩序を一度壊すことは「ゲーム」そのものを崩壊させかねない危険な綱渡りであるが、そのリスクを冒し、ルールを逸脱し、破壊し、再編集していくプロセス、つまり「ゲーム」を作り変えていくプロセスこそがシカールのいう「遊び」であるということである。
そして、どのように「ゲーム」を作り変えていくかを決定していくその瞬間瞬間に、プレイヤーが主体となって創造力や表現力を発揮できる余地がある。
少し抽象度が高いため、再び大富豪の例にのっとって説明しよう。大富豪を「8切り、縛り、Jバックあり」という同じルールでやり続け、大富豪から大貧民までの順位を繰り返し付けていても、それはルールの中でただ競い合っているだけである。プレイヤーはどの順番でカードを出すか、パスをするかを選択するだけの、「ゲーム」の支配下の存在でしかない。
シカールが言う「遊び」とは、ルールで遊ぶこと、つまり「じゃあ次はJバックはなしで、5スキップはありにしようぜ」「次大貧民になったら恥ずかしいエピソード発表な」と、ルールそのものを足したり引いたり、元のルールに新しい要素を取り入れたりして、ゲームを作り変えていくことである。
このときようやくプレイヤーは「ゲーム」の支配下の存在から、どのように「ゲーム」を「遊ぶ」かを選択できる存在になり、その選択の仕方に創造力や表現力を発揮することができるのである。
ここで考えていたのはサークルを「面白い」ものにし続けるための方法だが、その方法のヒントが上で見たシカールの遊び観の中にあるのではないだろうか。
つまり、ルールそのものも「遊び」の対象に組み入れるようないたずらな遊び心で、既存の秩序を切り崩し、自分なりに「ゲーム」を作り変えたり、新しく生み出したりするときの「面白さ」がサークルには必要なのではないだろうか。
本誌の判型や用紙を前号までのものから大きく変えたことはまさしく、早稲田リンクスというサークルにおける秩序の作り変えであり、そのような「遊び」の実践であると言ってよいかもしれない。従来「判型や用紙を変えてはならない」という意識が明文化された形で強く共有されていたわけではないが、なんとなく通例的に引き継がれており、ささやかな了解として機能していた。
私たちの実践ではサークルの基盤となる秩序というより、そのようなささやかな了解を切り崩した結果、雑誌という物質そのものまでも「遊び」の構成要素に組み込むことができたような感覚がある。
長い目で見てサークル運営にいい影響を与えられているかどうかはまだ評価できないが、少なくとも筆者にとっては、その過程が本能的に「面白い」と感じられたことをここに報告したい。
私たちの潜在的な「遊び心」
ここまで述べてきたことを振り返る。サークルというふわっとした集団をどう維持するかという問いを起点に、まず、サークルが自己目的的な「ゲーム」の形態として存在していることを分析した。しかしサークルという「ゲーム」はその「面白さ」を保ち続ける必要があるという問題を抱えているため、シカールの論を参考に、ルールを自らの手で操作し自由に「ゲーム」を作り変えていくその瞬間に、創造性や表現力を発揮できるのではないか、ひいてはそれが「面白さ」の維持に繋がるのではないかと提案した。
サークルが「ゲーム」であることを認識した上で、「ゲーム」を作り変えていく「遊び」に挑戦することが、サークルをうまくマネジメントするための一つの方法である、というのが筆者の主張である。
既存の秩序を切り崩し、自由に「ゲーム」を作り変えていくその瞬間に「面白さ」を見出す。こう書いてみるとなんだか難しいことのように思えるが、小さい頃の私たちはそんなことばかりして遊んでいたのではないだろうか。
学校からの帰り道、一定のパターンで並んだ路面のタイル模様をリズムゲームのように踏みながら歩いていたし、家に持ち帰って親に渡すべき学級通信をくしゃくしゃに丸めてキャッチボールをしていた。
それらはまさに既存の秩序を読み替え、逸脱し、新たな「ゲーム」を作る営みだ。そのような、私たちが潜在的に秘めている「遊び心」を存分に解放し、その「面白さ」を味わい続けることができたら、仲間は自然とそこに集まり、輪ができるのではないだろうか。
(註1)ヨハン・ホイジンガ 著/高橋英夫 訳 (1973)『ホモ・ルーデンス』中公文庫.
「遊び」について論じるなら避けては通れない重要な一冊であり、「遊び」に対する思考の基礎を形作った。現代のゲーム・スタディーズにも大きく影響を与える。
(註2)ミゲル・シカール 著/ 松永伸司 訳(2019)『プレイ・マターズ 遊び心の哲学』フィルムアート社.
(註3)松永伸司(2023)「まじめな遊び、ふざけた遊び」『広告』 417, pp. 120-158.
この記事ではホイジンガとシカールの遊び観の違いをより詳細に解説しており、本稿を書く際にはスポイルスポートについての部分以外にも大いに参考にした。