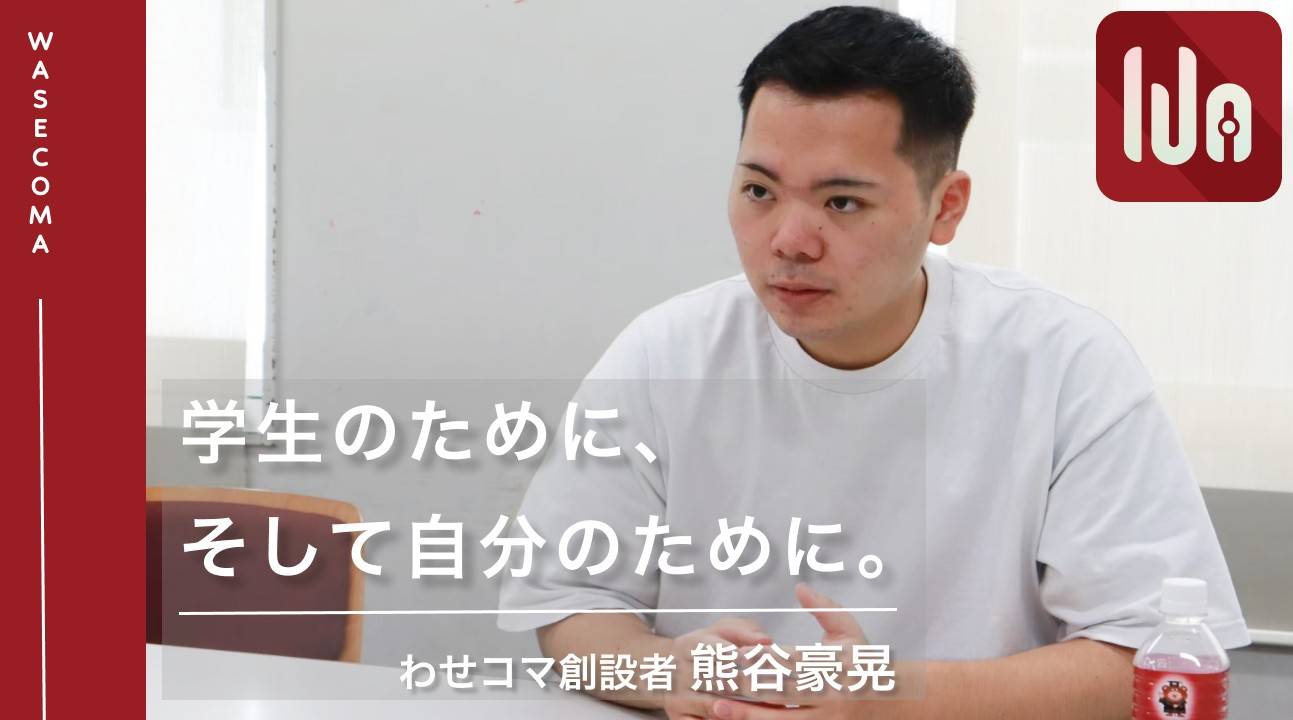早稲田に通う友達に時間割を尋ねて、「わセコマ」の画面を見せられなかったことはありません。
早稲田生の多くが利用する時間割管理アプリ「わせコマ」は、当時早稲田の学生であった熊谷豪晃(くまがいたけあき)さんによって開発され、現在はわせコマ運営サークル”Sodai.”を通じて、現役早大生の手によって運営されています。
わセコマはどのように始まり、どのようにして早稲田生に絶大な人気を誇るサービスにまで上り詰めたのでしょうか。開発者の熊谷さんにお話を聞くと、2つの原動力が見えてきました。
—はじめに、どのようにわせコマが始まったのかを教えていただけますか。
僕が大学2年の頃、「学生のため」のサービスであるはずの時間割アプリが、単に企業が収益を上げるためのプラットフォームになっているということに違和感を覚えたことがきっかけでした。
そこで、まず、大学のシステム関連を担当している部署に企画書を持って行き、「大学側でこういうアプリを用意できないのか。用意できないなら自分でやるから、例えば資金提供をしてもらえないか。」と掛け合ってみたんです。
そうしたら門前払いというか、「何いってんの君」って、すごく冷たい反応をされて。そこで、「大学側が相手にしてくれないなら自分でやるしかない」ということでわせコマを始めました。
—熊谷さんが卒業されるころにはわせコマは約3万ダウンロードもされていましたよね。
サービスを始めたのが大学2年の秋、つまり2019年の10月ですね。
その10月に「来年の4月までに1万ダウンロード達成」という目標を掲げました。
勝負のタイミングを新入生が入学してくる翌年春に設定して、それまでの半年は下積みの期間だと思って、機能のブラッシュアップや、サークル情報や講義の口コミ情報の拡充など、新入生に「使いたい」と思ってもらえるようなサービスの土台作りに注力しました。
そうして準備して、春を迎えると実際に1万DLを達成しました。その後も、また次の秋までに1万5000DLという目標を立てては達成して、その次の春までに2万DLという目標を立てては達成して、というのを繰り返して、気付いたら3万DLを達成していました。
そうこうしているうちに、僕がもう就職しなきゃいけなくなったので、2021年の秋に引退して、後輩にサービスの運営を引き継いだ、というのがこれまでの大まかな流れですね。
—開発する前にまず大学側に掛け合ってみたとのことですが、それにはそれなりに勇気が必要かと思います。
最初に大学側に掛け合ったこと自体は大したことだとは思っていなくて、わからないことを先生に聞きにいくような感覚でした。
一度聞いてみて、仮に「このシステムを実現するためには大学側の〇〇という問題が障壁となる」とか、「〇〇といった理由から活動を支援することも、認めることもできない」と言われ、その場では構想が形にならなかったとしても、それはそれで、大学側の意見や視点を得られたことになるので自分にとってプラスだと考えていました。
自分の考えが正しいのかどうかは、聞いてみなきゃわかんないし、やってみなきゃわかんないですよね。

—資金はどう調達していたのですか。
自分の持ち出しです。なので、最初の方はコストを節約するのに本当に苦労しました。
自分達で開発していたため、開発費はかかっておらず、サーバーもFirebase(Google社)を使い、無料プランのデータ量まで抑えるために、画像を全部圧縮してからアップロードするなどして、ランニングコストも極限まで削減していました。広告宣伝に関しても、キャンパス中にポスターを貼りまくっただけだったので、かかった費用は印刷費ぐらいだったと思います。
そうやってなんとかやり繰りして、サービスを維持していました。
—わせコマをよりよいものにアップデートする時、「よい」の基準はどこに据えていたのでしょうか。
学生のためになるかどうか、が唯一の基準です。
そもそもわせコマは、「学生のため」を第一に考えて始めたサービスでしたので、機能の追加やその他諸々に関して決定する時は必ず、「学生のためになるかどうか」という基準だけで判断をしていました。
なので、どれだけ大きい仕様変更でも学生のためになるのであれば何日かけてでもやっていましたし、逆に、企業による時間割アプリの間でチャット機能の導入が流行っていた時期では、「学生は時間割アプリではチャットしないだろう」と直感したのでで導入しないという判断をしました。自分自身も学生であったので、一人の学生、一人の利用者の視点で考えることを大事にしていました。

—空き教室検索という珍しい機能もありますよね。
珍しいですよね。空き教室検索というサービスは少なくとも僕が入学した時には、他のwebサービスも含めてどこにもなかったんです。僕自身、空き教室をよく使っていましたが、ドアを開けてみても授業をやっていて使えなかったり、空いていると思って使っていたら人が入ってきたりして、それがすごく面倒くさくて。空き教室を事前に調べられたらいいなと思って導入しました。
—導入したいと思ったらすぐに導入できるものなのですか?
機能によってそのハードルは異なります。例えば、空き教室検索機能の導入にあたっては、マスタデータを作成するために大学構内の全教室を歩いて回りました。
全てのキャンパスの全ての建物を一番上から下まで回って、どこに何という名前の教室があるのかを調べました。そうして作成した全教室データと、シラバスから抽出した各講義の開講時間と場所を紐づけることで、空き教室を割り出しているんです。
なので、皆さんが今調べている空き教室の情報は、超アナログな作業で収集したデータがもとになってるんです。かなり根性が必要な作業でしたね。
—わせコマは非営利で始められたと聞きました。ボランティアのような一面もあると思うのですが、そういった意識はありますか?
もともと、入学して一年半くらいは、サークルでずっとボランティア活動をしていたこともあり、ボランティア精神のようなものは自分の根底にあると思います。そのサークルでは、ベトナム郊外に住む学校に通えない貧しい子供たちへの奨学金支援等を行っていたのですが、そこでの経験にすごく影響を与えられた気がしています。
—それはどのような経験だったのでしょうか?
約2週間ほどの現地滞在は新しい発見の連続で、毎日が刺激的でした。
しかし、その中でも強く印象に残っていて、今でも僕の心に引っ掛かってることがひとつあって。
大学1年の夏、初めて参加したベトナム渡航の3日目に、ホーチミン市郊外の学校を視察するプログラムがあったんです。その帰りバスでの出来事でした。車道と車道の間にちょっとだけ人が歩ける歩道があって、僕が乗っているバスがそばに停まった時に、ちょうどその歩道に居た小さい四、五歳の女の子と目が合って、何かを訴えかけるようにずっとこっちのほうを見てくるんです。左手には宝くじの券を大量に持っていて、右手にはかごを持っていて。
あの子は一体何をしているんだろうと。
その時は何も分からず、すぐに別の方を向いてしまったのですが、ホテルに帰ってから先輩に聞いて分かったのは、ベトナムでは親が子供を使ってモノを売らせることがある、ということでした。
まだひとりでは眠れない程の歳の子や、ベトナム戦争の爪痕とも言える地雷によって片足を失った子供たちに宝くじとかごを持たせて街を歩かせ、その姿を餌にして人々の同情を買い、そして、子供が売って得たお金で生活をする。それが、ベトナムが抱える貧困の現状だったのです。
要するにあの女の子は、炎天の中、家計を支えるため、ひとりぼっちで、ただひたすら宝くじを売り歩いていたんです。僕はバスの中にいて、目が合っていたのに何もできなかった。
その「何もできなかった」っていうのが今でも心に引っかかっているんです。あの光景を今でも鮮明に思い出すくらい、記憶に残っています。すごく無力感があったというか。
この出来事が、僕の中のボランティア精神をより一層強めたことは間違いありません。
目の前に困っている人がいて、自分がその人の力になれるのであれば、躊躇せず手助けをしてあげたい。その気持ちがすごく強まりました。この体験が、わせコマの活動の原動力のひとつになっていたと思います。

—弱い立場にある人が、その意志に関わらず商売道具として利用されてしまっているというのは、学生が何も知らずに情報を入力してそれが企業に使われているという構造と似ていますね。ボランティアサークルに入ろうと思ったきっかけは何でしたか?
そうですね。ボランティアサークルについては、まさに偶然の出会いでした。
大学の必修科目で隣の席になった人が、野球サークルとボランティアサークルに入っている留年生だったんです。僕も野球サークルに入りたかったので話を聞いてみたら、「野球サークルは飲み会がメインみたいになっちゃってるんだけど、ボランティアの方は面白いよ」と言われたんです。「じゃあ一回行ってみます」って言って実際にミーティングに参加してみたら本当に面白くて。少し興味が湧いたのでそのまま入会を決めました。
—最初からボランティアサークルに入ろうという感じではなかったんですね。
そうですね。ボランティアサークルに入るまでは、そういうボランティア活動みたいなものに対して、なんかネガティブな印象というか、単なる自己満足や偽善じゃないか?とまで思っていました。
—無償でやるということは、見返りが期待できない状況だと思うのですが、熊谷さんはなぜわせコマの活動を続けられたのでしょうか。
僕が活動を続けられた理由を考えてみると、二つの軸があったと思うんです。
一つは今言ったような、ボランティア精神というか、本当に学生のために何かしたいという想い。もう一つは、大学側に突っぱねられた悔しさです。くじけそうになっても、ある時は学生のために、ある時は自分の中にある悔しさを晴らすために、日々どちらかの自分と闘いながらサービスを続けていました。他人志向の動機と自分志向の動機の二つがあったことが、辛く、苦しい状況でも諦めずに活動を続けられた要因だったと思います。

たぶんみんなどちらかは持っているんです。「誰かのために何かをしたい」という貢献意欲や使命感であったり、「悔しいから見返してやる」という反骨心であったり。どちらかを持ってることは多いけど、両方揃うことって少ない。
自分志向の動機だけで活動していると、所詮、自分以外に喜ぶ人は誰もいないですし、その活動は自分を満たすためのツールでしかないわけです。また、努力の量は自分の満足値に依存しますから、「別にこれでいいか」って思ってしまったら、そこで全てが終わってしまう。
成功の限界を自分で決められてしまうんですよね。
一方で、他人志向の動機だけあっても、自分に見返りがないので簡単にやる気を失ってしまいます。だからなかなか行動に移せない人や、行動に移せても継続できない人が多いと思うんです。
僕の場合は、その2つの動機を持っていたことでモチベーションをうまく維持できたんだと思います。ある時は人のため、ある時は自分のためという両方のエンジンがなくちゃいけない。
—無償で活動を続けていく中で、予期せぬ見返りはありましたか。
やはり一番は、知り合いから赤の他人まで、多くの学生から「わせコマ使ってます」「めっちゃ便利です」と言ってもらえたことですね。
時間割アプリって、特段不満がなければ他のアプリには乗り替えませんよね。わせコマをリリースした当時は、乗り換えてくれる人がなかなかいなくて、同級生にすごくたくさん声をかけて、やっと三、四人がダウンロードしてくれたんです。
リリース当初はそうやってすごく苦労したので、わせコマのダウンロード数が増えていった後に、予期せぬ人から「ありがとう」っていう言葉をもらえた瞬間はすごく嬉しかったですね。
それから、わせコマを通じて知り合って、自分を支えて下さった周りの方々との出会いも、とても大きな財産であると感じています。
わせコマをより多くの学生に使ってもらうための施策についてや、学内の環境改善とわせコマが大学に貢献できることについて議論させていただくため、大学関係者のもとへは何度も足を運ばせていただきました。また、早稲田商店会の皆様には、わせメシコラボから「1カ月無料食べ放題キャンペーン」といった無茶な企画まで散々お世話になりました。
早稲田にフジテレビのロケが入ったときにはその調整役を担わせていただきましたし、LINE社とはオープンチャットを用いた協業の機会もいただきました。会長が早稲田出身ということもあり、イオンさんには大変お世話になりました。また、楽天さんにも「わせコマ」というサービスに大変興味を示していただきました。
最終的には、わせコマ運営サークルには約60名もの優秀な学生が参加してくれて、後輩たちからも沢山の刺激をもらいました。
大学2年の夏に、もしわせコマをつくらずに、面倒くさいからいいやって諦めていたらこれらには全部出会えなかったです。

—わせコマの活動を振り返ってみて、今学生に伝えたいことはありますか。
先ほど申し上げたように、他人志向の動機と自分志向の動機が揃うと、新しいことに挑戦しやすい。でも、その両方が揃っても、やっぱり失敗を恐れてしまう人が多いかと思います。
そこで一つ言えるのは、別に失敗してもいいのが学生なんです。いくら失敗したって、いくら自分の考えが否定されたって、最終的には周りの学生と同じく、「大学卒業」という肩書きを得た人になるんです。社会人のように立場を失う心配をする必要はありません。
学生時代とは、「失敗が許されるボーナスタイム」なんです。
学生時代の失敗は100%次に生きる。だからこそ挑戦は意味のある経験だと思うんですよね。
そういう意味で、学生生活というものは、セーフティーネットを張ってもらっていて、その分自由に行動できる、すごく恵まれた時間だと思います。学生の期間を人生の夏休みと捉えて遊びに充てるのもいいのですが、やりたいことがあるのに消極的になって遊んでいるのであればもったいないと思います。学生という立場に良い意味で甘えさせてもらって、失敗など気にせずに積極的に挑戦してみてください。